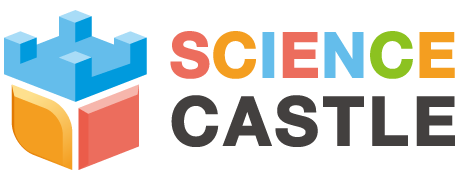研究コーチ登録のご案内
平素より、リバネスの教育活動、研究活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
リバネスでは、サイエンスキャッスルほか様々なプログラムを通じて、研究を始めた10代(中学、高校、高専、ホームスクーリング)に対し、現役の大学院生や研究者が研究活動を伴走していく「研究コーチ」事業を行っております。2023年度はのべ57名の研究コーチが活動してまいりました。これは、2012年のサイエンスキャッスル発足時はリバネスの社員だけで行っていたプレゼンテーション指導やポスター演題審査を、広く大学院生や大学の研究者、企業の研究者からの登録を受け付けて体制を拡張したものです。
10代の駆け出し研究者が求めているもの
もし自分が中学のときに研究を始めていたら、と想像してみてください。「学校内に研究のことを相談できる先輩がいない」「研究発表の練習は顧問の先生ぐらいとしかしたことがない」という声をリバネスでは実際に聞いてきました。SSH指定校のように交通費のサポートを受けられるケースもありますが、地理的に近くの大学にたまたま専門家がいない、といった場合や、高大連携の枠組みがあっても研究指導までは行ってもらえない、という事情を鑑み、研究コーチはオンラインでの指導を基本とし、地理的制約や時間的制約をできるだけフレキシブルに対応できるように取り組んでいただいています。
研究コーチの皆様には、ご自身が学んでいった経験をもとに以下のようなことをお伝えいただけると幸いです。
- 自分の研究分野に関する情報
- 先行研究の調べ方
- 仮説の立て方や、研究計画の立て方
- 実験のやり方
- 伝わりやすい発表や記述の仕方
- あなた自身のこと(なぜその研究をしているのか、研究者としての将来像など)
どういった10代と組んで進めていくかは、コーチとしてご協力いただけるかたの登録情報(専門分野のキーワードなど)をもとに、研究テーマに応じて割り振る形をとっています。しかし、必ずしも「同分野、同様の方向性」の研究者どうしでペアにするわけではありません。10代が提出するテーマも多様さを増す傾向にあり、また、研究コーチの専門性もさまざまな方向にむかっていることが特徴としており、分野を超えた組み合わせになることが多くなっています。
研究コーチがあなたにもたらすもの
研究コーチ事業は、次世代の研究を応援することを目的としています。が、それと同時に研究コーチを務める研究者本人にも「応援したことが返ってくる」ことを強く意図しております。これは実際にリバネスの社員がプレゼン指導にあたったり、研究を深めるディスカッションするなかで感じたことでもあり、「研究コーチ」のやりがいや醍醐味につながっていると思います。
研究コーチを務めてくださった方々の声、をご紹介します
- 日頃の研究室での学生指導の気づきを得ることができました。
- 一緒に活動した高校生が、研究の道を選んでくれて嬉しかった。
- 論文にとらわれがちな毎日で、次世代の純粋な好奇心にふれることで、研究を楽しむ気持ちを思い出しました。
- 子どもたちのの研究発表の熱意、情熱、視点、発想が素晴らしく大きな影響を受けた。
インタビュー記事の形でもご紹介させてください。
具体的に何をするのか
研究&プレゼンテーション指導
主に口頭発表者とペアになり、研究の進捗を口頭で聞きながら、期限内に研究成果が得られるように軌道に乗せていくための助言をしていただきます。「熱い気持ちはある、でも研究として深めるにはどうしたらいいか分からない」状態であったり、もっとわかりやすく見せたいがどうしたらよいか、という向上心に寄り添い、研究コーチ自身の言葉で語りかけてあげてください。助言は、リバネスのコミュニケーターとタッグを組み、方向性を相談しながら進めることができます。
ポスター審査員
大会においては、ポスター審査員をつとめていただきます。これは10代の研究者、研究コーチが一同に会する貴重な機会となっています。会場での対話することで、10代の研究者たちは、研究の達成感や次へのやる気をたぎらせていきます。一方、研究コーチも、”後輩”が奮闘する姿をみて大変刺激をうけてきました。
参考までに2023のポスター審査員の依頼仕様をご紹介します。
研究コーチとして、ご協力いただける方は以下の登録フォームより、専門分野やキーワードをご登録お願いします。ご登録情報をもとに、10代の研究テーマとのペアリングを行いますので、その際はリバネスからご連絡さしあげます。
今後とも、リバネスの教育、研究活動にご理解とご協力をよろしくお願いします。