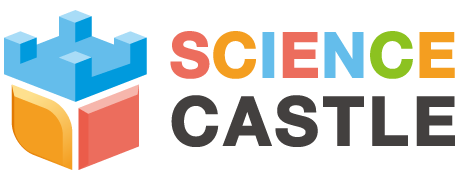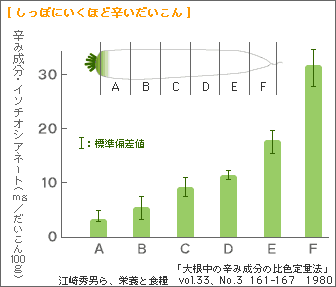- お知らせ
- 関西大会のお知らせ
とつげき!となりの参加校!vol.6 大阪府立住吉高等学校
2014.12.17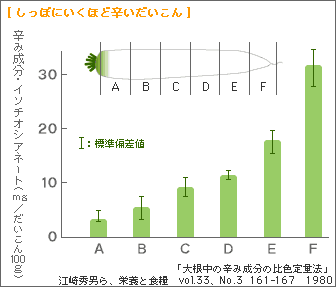
こんにちは!
リバネスの石澤です。
先日、大阪府立住吉高等学校に行ってきました!
住吉高校は、全部で2件(口頭発表はポスターも掲示するので実際は3件) 、どちらも英語発表にチャレンジです。
Chemical Ecology of the Brassicaceae Plants ( 大阪府立住吉高等学校 サイエンス部 )
私達は、アブラナ科植物が持つイソチオシアネート(ITC)という物質に興味を持ち、アブラナ科植物とITCの関係から、アブラナ科植物の生存戦略について研究した。実験の結果、発芽直後や、病気に感染した後、天敵に食害を受けた後などにITC濃度が上昇していることや、種の存続に重要な器官である種子と花芽では多くのITCが生成されていることが分かった。また、アブラナ科植物最大の天敵であるモンシロチョウの幼虫は、ITC含量が少ない葉を選んで食べていることが分かった。これらから、アブラナ科植物はITCを用いて天敵を忌避し身を守っていると結論付けた。これからは、ITCを通した生態系全体についても研究していきたい。
The color distinction experiment of jellyfish ( 大阪府立住吉高等学校 SS科学Ⅱクラゲ班 )
We used and investigated “takokurage” about change of movement by light and a color. And change by them was able to be checked.
どちらも身近な、面白い着眼点からスタートしているのが印象的でした。
サイエンス部の研究では、アブラナ科の植物として大根を対象にしています。
確かに個体や部位によって辛みは違いますよね?
その理由と天敵との関連から研究を発展させているんです。
実際に、どんな結果が出てきているのか………は、ぜひ当日の発表を聞いてみてください!
ちなみに、カゴメ株式会社では、こんな調査が掲載されていました
<カゴメ株式会社の野菜大全より引用>
もう1つのクラゲ班の発表では、「くらげは色を識別できるのか?」という疑問にチャレンジしています。
もし、色を認識しているとしたら、何のためなんでしょうか?
まだまだデータ数は少なめでしたが、オリジナルの実験系を設定している辺り、今後の展開が楽しみでした!
さて、発表を聞かせてもらって、一番感じたのは「内容を盛り込み過ぎてもったいない!」ということでした。
たくさん実験をしているので、その分たくさん結果が揃っていて、それぞれに解釈があって………
全部発表したい!!その気持はわかります。
ですが、当日の発表時間は限られています。
その中で、自分たちの研究の魅力を最大限に伝える必要があるため
改めて、以下の2点を意識した方が良さそうです。
・伝えるポイントを1つに絞る
・そのポイントを伝えるのに必要なデータだけ示す
みなさんも、今一度、自分の発表を見なおして見て下さいね!
実は、今回はエントリーしていませんが、もう1件研究成果を見せていただきました。
「髪の毛が痛む原因を探る」ということで、 色々な素材でエクステを洗い電子顕微鏡で調べていました。
タバスコで洗うと痛むとか、やっぱり蜂蜜やオリーブオイルは髪にやさしいとか 予想通りのものもあれば
以外な結果になった素材もあったようです。
こちらは、ぜひ来年発表して欲しいですね!
ポイントまとめ
⑪伝えるポイントを1つに絞る
⑫そのポイントを伝えるのに必要なデータだけ示す